 浜名湖の雄踏の漁師さんに細かい魚たちを分けていただく。
浜名湖の雄踏の漁師さんに細かい魚たちを分けていただく。中に外套長50mmほどのジンドウイカと、10mm以下のミミイカが混ざっていた。
連れて帰ってきたら食べる、と決めているので、「ねこた(ヒイラギ)」を煮た煮汁で、そのまま煮た。
ものすごく小さな個体だけれど、温暖化対策のためというか、自然保護は「食べられるものを有効に利用する」ことが基本だ、と思っているので、無駄にはしない。
無駄にはしないどころか、ジンドウイカは柔らかく、しっかりイカらしい風味がある。
ミミイカなど極小なのに、「イカなのにタコ」的な食感があって、ワタに味があった。
口寂しい、昼下がりにちょうどよいおやつとなる。
浜名湖さん、ありがとさん。
コラムの続きを読む
 ボクはあまり集中力がある方ではない。
ボクはあまり集中力がある方ではない。調べ物をしているときは、別のことができないし、外出も不可能だ。
そんなときよく作るのが炊き込みご飯である。
今回は塩サクラマスがあったので、まず解凍させて、時間をかけて香ばしく焼き上げる。
粗熱がとれたら水飯の用意ができたところに入れ、刻み生姜、少量の酒・醤油を加える。
塩サクラマスに塩気があるので醤油は風味づけ程度だ。
炊飯は、米を洗うが数分、水加減して浸水30分、炊くのはたぶん10分、蒸らし10〜15分である。
浸水の30分で塩サクラマスを焼き上げる。
つきっきりでやらなくてもいい上に1時間以内で食べられる。
炊き上がりを食べたら、鼻に抜ける香りにうっとりする。
うま味を放出しているはずのサクラマスの身に強いうま味は感じられるし、甘味がある。
混ぜ込んだ刻んだミョウガが、いい味を出している。
当たり前だけど、サクラマスのうま味に満ちた飯のうまきことよ。
みそ汁を作る間もなかったので、炊き込みご飯のみ2膳で、こんな日もある、ありすぎるボクだった。
コラムの続きを読む
 浜名湖の雄踏漁協で「ちんた(クロダイ)」をいただいた。300g以下を「ちんた」、以上を「くろだい」という。今回の体長19cm・195g は競りに出すともなく、廃棄もしくは放流することになるらしい。以上は前回もかいた。
浜名湖の雄踏漁協で「ちんた(クロダイ)」をいただいた。300g以下を「ちんた」、以上を「くろだい」という。今回の体長19cm・195g は競りに出すともなく、廃棄もしくは放流することになるらしい。以上は前回もかいた。片身を刺身にして、あらをあら汁にした。
骨つきの半身はムニエルにする。
横道にそれるが、サイトの運営上しかたがなく、特定のサイトなどを見ることがあるが、非常にいかがわしい、というか薄汚い。
当たり前の魚を「超レア」だとか、もっとも嫌いな言葉「究極の」とか、「これ以上の魚はない」、「これが究極の料理法だ」などと書いてある。
世の中に特別なものは存在しない、と思っているのでこのような言語を使うこと自体、愚かしいと思っている。
魚は日常的に当たり前に食べてこそ、日本の自給率を上げることが出来るのに、これじゃ逆効果だし、自然に優しくない。
ということで、今回の「ちんた」など買ったとしても安いものだし、珍しいものでもない。
ボクのケ(日常)の日のお昼に、至って平凡にムニエルにして食べた。
これに、いただきものの食パン1枚(高そうなパンで少し甘みがある)と日東紅茶とトマト1個のお昼だけれど、トマトが大きいので腹持ちがいい。
クロダイの骨つきの半身は、塩コショウして小麦粉をつけてじっくりソテーしただけ。
ムニエルは意外なくらい難易度が高い料理だけど、失敗しても失敗したと言うほどまずくないのがいい。
タイ科のムニエルの特徴は、ソテーの仕方次第だが、皮がかりっと香ばしく上がり、身にしっとりと潤いが残ることだ。
自画自賛はいかんが、今回は非常に上手にソテーできた。
「ちんた」のムニエル、滅法うまいではないか。
皮を食べただけでも御馳走だし、身に甘味がある。
今回はパンに合わせたが、ご飯に合わせるときは醤油をたらすとよりご飯向きになる。
今回の問題点は高そうな食パンに甘みがありすぎたことだけだ。
魚料理に合わせるときのパンには、あまり上等なのはいらぬ。
コラムの続きを読む
 浜名湖の雄踏漁協で「ちんた(クロダイ)」をいただいた。
浜名湖の雄踏漁協で「ちんた(クロダイ)」をいただいた。浜名湖では300g以下を「ちんた」、以上を「くろだい」という。
今回の体長19cm・195g は競りに出すともなく、放流することになるらしい。
ちなみに1㎏前後は競り場に生きた状態で並んでいたし、直売所では刺身が売られていた。
これを活かして持ち帰っている途中、高速道路上で後ろからバシャバシャと音がする。
PAに入って見ると、「ちんた」が大暴れをしているではないか。
仕方なく締めて、血抜きしないで持ち帰った。
暴れたせいで尾鰭がぼろぼろ、決していい状態とは言えない。
帰り着いた日に下ろして翌日刺身にする。
大きさも、漁の後のボクの締め方にも、期待できるところはなにもない。
ところが、これがうまかったのである。
脂はないが、味がある。
口に入れてすぐに甘味とうま味があり、中だるみがない。
「ちんた」は「ちんた」なりのおいしさがあるのだな、なんて思ったものだ。
ついでに言えば水域での汚れや汚染に影響を受けやすい魚だが、浜名湖はこの点からしても大丈夫らしい。
コラムの続きを読む
 浜名湖の東西はともに遠江の西で、湖を挟んではいるが同じ地区だと思っていた。
浜名湖の東西はともに遠江の西で、湖を挟んではいるが同じ地区だと思っていた。実際に行って、いろいろ話を聞くと、食文化はまったく別で、魚の評価も違っていた。
例えばヒイラギは、浜名湖の西の湖西市鷲津・入出では「ぜんめ」、「ぜんな」、東の浜松市雄踏では「ねこた(猫またぎ)」という。
西では食べ物で、東出は捨てる物だ。
東、雄踏漁協の漁師さんにお願いしなくても、いただくことが出来たのが「ねこた」である。
それでは浜名湖のヒイラギは、東西で味が違うのだろうか? というと、そんなことはない。
「ヒイラギはとてもうまい魚だ」ということを東の漁師さんにいただいたヒイラギで、改めて思う。
棘をハサミで切り取り、粗塩でぬめりを取って、水洗い。
あとはざっと煮るだけ。
高知市の漁師さんで、ぬめりも味だという人がいるので、ぬめり取りは不要かも。
身離れがよく、身に甘味があり、とってもおいしゅう、ござんした。
コラムの続きを読む
 カツオの切り身をあぶる地域は少なくないが、切りつけて塩を手につけてたたくのは高知県だけ、なのだろう。
カツオの切り身をあぶる地域は少なくないが、切りつけて塩を手につけてたたくのは高知県だけ、なのだろう。高知県の旅では中土佐町、いの町で実演しているのを見ている。
実に手慣れたもので、あぶる、切る、塩をつけた手でたたく、と次々に出来上がる。
あまりにもうまそうなので、思わず買ってしまいそうになる。
この本来、カツオで造る、「塩たたき」を「だるま(メバチマグロの幼魚)」で造る。
出来上がりを盛り付けて、すだちを1個全部搾り、みょうがに青じそに、にんにくを天盛りにした。
仕上げに追いスダチをする。
塩気は充分なので、スダチと香辛野菜だけの単純な組み合わせで食べる。
脂ののった「だるま」は、うま味も非常に豊かで恐るべきうまさである。
スダチ2個を搾ったが、もっと多くてもよかったかも。
香酸柑橘類の旬はまだまだ遠い。
コラムの続きを読む
 浜名湖に散らばる角網(小型の定置網)で揚がる魚の種類は非常に多い。
浜名湖に散らばる角網(小型の定置網)で揚がる魚の種類は非常に多い。大型魚はスズキ、クロダイ、ボラなどだが、むしろ小型魚であるコノシロ、はんだ(サッパ)、ねこた(ヒイラギ)、夏はぜ(ウロハゼ)などが多いようだ。
浜松市雄踏では「はんだ(サッパ)」は当日見た限りでは、競りに出すことがなく、廃棄されているようだった。
これは浜名湖西部の鷲津でも同じである。
ちなみにサッパは大きな括りではニシンやマイワシに近い魚で、腹部の底の部分に非常に硬い鱗があるのが特徴である。
水揚げを見ていたとき、雄踏漁協の漁師さんたちに分けていただいたので、持ち帰って計測して食べてみた。
それほど面倒な料理ではなく、岡山県で普通に作られている焼き漬けである。
じっくり時間をかけて素焼きにし、二杯酢に1日漬け込んだだけ。
酢と相性がいいのもあるが、非常にこくのある味で、濃厚なうま味が舌に残る。
サッパという魚は、小骨が硬くて多いという二重苦を背負っているが、うま味の豊かさという点ではニシン類の中でもトップクラスである。
岡山県人をして、「ままかり料理」の第一にあげる人が多いわけがわかる。
旅の後なので、静岡県藤枝市の志太泉 原酒を冷やして舌を洗う。
コラムの続きを読む
 山芋(今回は大和芋)をすって、大きめに切ったブツにかける、ので「山かけ」だ。
山芋(今回は大和芋)をすって、大きめに切ったブツにかける、ので「山かけ」だ。「山かけ」で重要なのは大和芋をおろし器でおろし、そのあとすり鉢に移して徹底的にすることだ。
コツと言ってなにもないが、すり鉢の中で容赦もなくする、する。
手が疲れるくらいすったら、すり鉢の中にぶつを入れ、こんどは和えて、和えて、和える。
これも徹底的に和える。
大和芋はこれくらいしないとブツと混ざらない。
ボクの場合はあれこれやらず、生醤油とわさびで食べる。
「だるま(メバチマグロの幼魚)」なのに、中心に近い部分にも味がある。
一日寝かしてブツにしたせいか、下ろしたてよりも酸味がある。
大和芋の強いねばりと微かな渋味とうま味が、酸味のあるブツとよく合う。
コラムの続きを読む

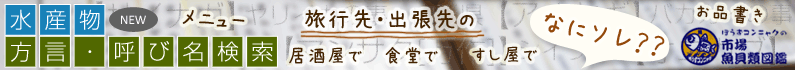

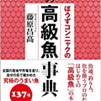 ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
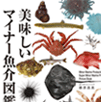
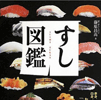
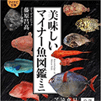
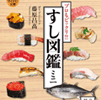

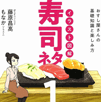 イラスト図解 寿司ネタ1年生
イラスト図解 寿司ネタ1年生




























